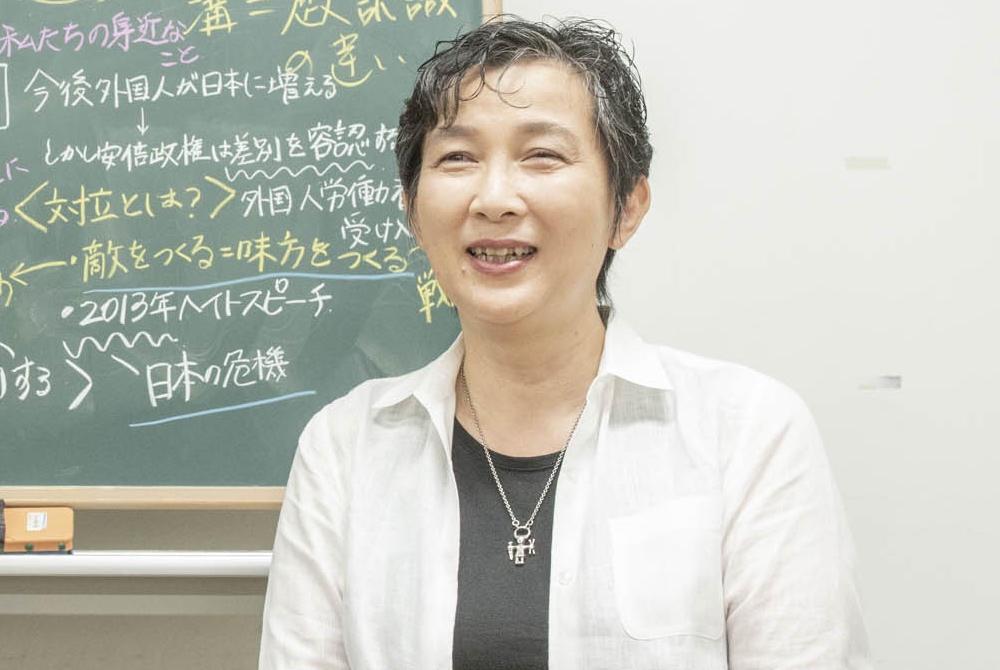
姉歯 曉先生
東京都出身。國學院大學大学院 経済学研究科博士課程 単位取得満期退学、経済学博士(中央大学)。現在、駒澤大学 経済学部 商学科 教授。主な著書に『農家女性の戦後史ー日本農業新聞「女の階段」の五十年』(こぶし書房)、『豊かさという幻想ー「消費社会」批判』(桜井書店)、『ジェンダーで学ぶ生活経済論』(共著・ミネルヴァ書房)など。

高畠 有美さん
経済学部現代応用経済学科3年。「姉歯先生はこちらの勉強したい気持ちに妥協せず応えてくださるので、素晴らしい環境だと思います。」
自主性が育まれ
双方向の学びができるゼミ


姉歯先生、高畠さん、本日はゼミについていろいろお聞かせいただければと思います。まず、先生の専門分野について教えてください。

よろしくお願いします。私の専門は経済学で、担当科目は消費経済論。消費という一番身近な窓口から世界経済や貿易、金融、労働といったあらゆる問題を見ています。

身近というのはどういうことですか?

一例をあげると、私たちは朝起きてから夜寝るまでさまざまな消費活動をしています。朝食べるパンも、着ている服もみんな商品として購入したものです。それらの商品がどこかの国の環境を破壊していないか、買い叩きなどで暮らしを破壊していないかなど、生活に根付いた消費からいろいろなことが学べるのです。

経済学と聞くと難しい印象ですが、誰にでも身近な問題なのですね。
では、ゼミのテーマはどういった内容がありますか?
では、ゼミのテーマはどういった内容がありますか?

たとえば、昨年度は日韓関係を歴史と現状から読み解くというテーマを扱いました。最近、特に沖縄の問題や日韓関係などさまざまな出来事がありました。多文化共生が言われる一方、ヘイトスピーチの問題もあります。それらの出来事が、日本の歴史に大きな関心を寄せる機会を提供することになりました。

硬派なテーマですね。

社会にある問題はすべて経済学に関連しているからです。学生たちの行動力はたいしたものでした。戦後の日韓関係を勉強していくうちに「戦争も加害と被害の歴史を今どう受け止めるべきか」について議論になり、それならということで、夏合宿でソウルを訪れ、占領期の跡を見学したり、文政権の経済政策や南北統一にむけての市民の反応などについて現地調査を行いました。

海外にも行かれるんですね。

実は、海外での合宿はゼミ始まって以来の出来事です。行き先は学生がみんなで話し合って決めました。

高畠さんは、実際に現地に行かれてどう感じましたか?

事前情報でわかっていたと思っていましたが、実際に現地で目の当たりにすると日本では気付かなかったことがたくさんあり、行った価値を実感しました。

たとえばどういうことですか?

日本にいると、Jアラートにおびえたりしていましたから、韓国はいつ戦争が起こってもおかしくない状況で危険な場所なのではないか、日本人だから何か言われるのではないかという不安があったのですが、実際訪れてみるとそんなことはなく、みなさんに優しくしてもらいました。反日感情などみじんも感じられなかったのが印象深かったです。

それは現地だからこそ感じられることですね。先生は合宿全体を通して、学生さんたちの取り組みをどう思われましたか?

まず、学生たちが作成した合宿のしおりが見事でした。たとえば、ソウルでの移動には、すべて電車を使いました。ソウルの地下鉄は多くの路線が行き交い、乗り換えを間違えると大変です。学生たちは、博物館や資料館を無駄なく回るために必要な情報をすべて集めていました。おかげで、みんな、迷うことなく現地にたどり着けました。

準備が入念ですね。

現地で回った中には、従軍慰安婦の博物館など、つらい内容のところもありましたが、分からないことは逐一ノートにとって、ハングルだけの情報はその場で翻訳して、一つひとつじっくり理解しながら前に進むということをみんなよくやっていました。

そういったことは先生がご指導されるのですか?

いえ、行き先を決めるところから事前準備まで、すべて学生が自主的にやっています。

それはすごいですね!

行く前に夏休みの間、週に3回も集まって事前勉強を行いました。韓国の問題だけでなく、たとえば日本国内で起こっているヘイトスピーチの問題については、自問自答しながら「それは表現の自由ではなく、人権を侵害する行為」という結論に行き着いたり、ネット情報に惑わされず、自ら考えて疑問が湧き上がると、当事者に話を聞いて学び、それをもとに討論する。これを繰り返していました。合宿までには、学生たちにそういった姿勢が身についていることに感心しました。

すばらしいと思います。

むしろ私が学生から学ぶことも少なくない。そういう双方向からの学びができるのがゼミなんです。
自分の好奇心や意見表明に
遠慮しない環境
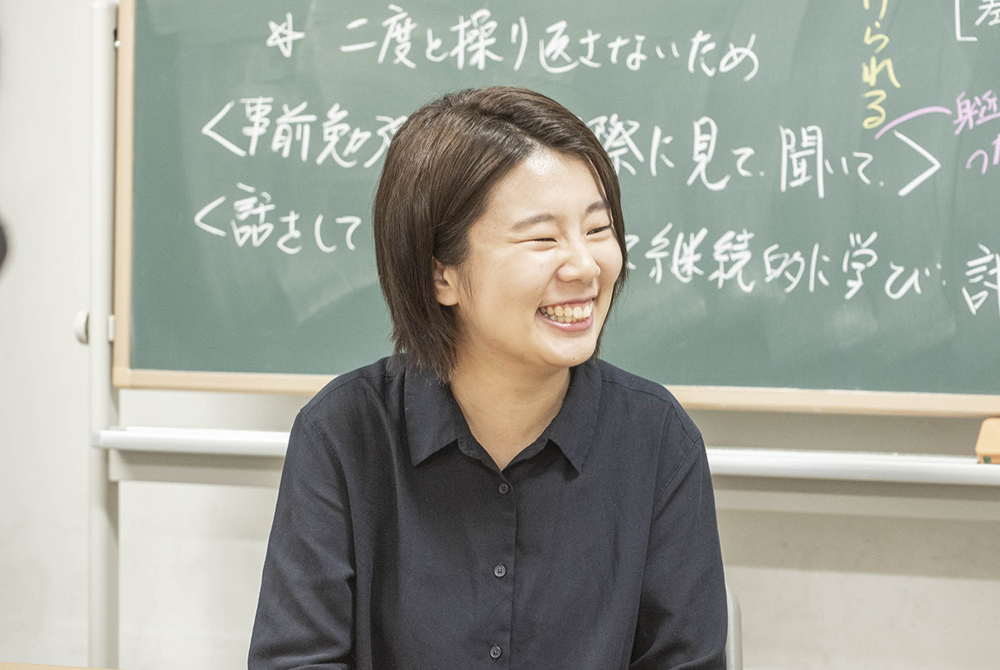

高畠さんはどうして姉歯ゼミに入られたのですか?

「大学に入ったからには、講義を受けるだけではなく、何か一つ自分自身で学び取り、それを形に残したい」と思ったとき、大学にゼミ活動というものがあることを知りました。ゼミは2年生からなのですが、1年生の秋に行われるゼミ説明会に参加し、興味のあるゼミをいくつか見ました。その中で、姉歯先生が研究されている内容が多岐に渡り、一つの切り口からいろいろなことが学べると感じてここに入ろうと。

高畠さんは現代応用経済学科で学科が異なりますが。

学部内でしたらどの学科の先生のゼミにでも入れるんです。それは他の大学との違いですね。

受け皿と選択肢の幅がすごく広いと感じました。それで先輩にもいろいろお話を聞かせてもらって・・・「一番厳しいゼミだ」と言われたのですが、好奇心が勝りました。

なるほど。ゼミが始まってからは、まずどういったことから活動を始めるのですか?

毎年、八王子セミナーハウスというところで2泊3日の春合宿を行うのですが、これに先立つその前の春休み中に、週に2回のゼミが行われます。そこでは、これからのゼミ活動に必要となる基本的なスキルであるレポートやレジェメ(報告の流れを追うためのもの)の書き方や討論の仕方などを学びます。そこで新ゼミ生は、自分で興味を持ったテーマを選び、実際にレジェメを書き、報告できるところまでの技術を身につけます。

春合宿はどういった内容で行われるのですか?

まず、新ゼミ生たちが選んだテーマを報告し、検討します。同時に、先生から提起された課題と関連書籍を全員が読んできて、その課題について討論します。

春合宿のための事前勉強の場では、ゼミの先輩が後輩に一対一で寄り添って、具体的なレジェメ作成等の指導をします。教える側としても、自分の勉強の不足部分を再確認してもらえる機会になりますし、ゼミもまとまりがよくなります。

ゼミ生自身が学び合う環境づくりを積極的に行っているのですね。先生から見られて高畠さんの印象はいかがですか?

最初から非常にストイックな印象でした。うちのゼミは仲良しの友だち同士で入ってくるような雰囲気ではないので、まず一人で研究室を訪れる時点でやる気が違います。彼女はゼミ以外もいろいろな活動をしていて忙しいのですが、学ぶことに貪欲です。たとえば、ゼミで歴史を学ぶ中で韓国問題を取り上げることになったとき、他大学で開催された韓国のマスコミに関する講演会に出かけて行く、韓国からの交換留学生と連絡をとるなど、とにかく、どんどん自分で道を切り拓き、人との繋がりや学ぶ環境をひろげていくことができる。そして、それを自分の身にすることができる。そういうエネルギーにこちらが背中を押されています。

一般的な日本の大学生には今ではなかなかみられない姿勢だと思います。

ゼミの雰囲気がそういう勉強がしたい意欲をかきたててくれるんです。

「一人一人の知的好奇心を皆が共有していく、そして表明に遠慮しない」というのが姉歯ゼミの大前提です。
卒業後に役立つ社会人スキルも身につく!


先生がゼミ活動で大切にされていることは何でしょうか?

ゼミ生たちが選択する研究テーマが、単なるインターネット上のニュースとか流行の企業の研究とか単純なものにならないようにすることです。たとえば国際金融や国際経済、社会問題などを含めて考えていかないと解決できない。そういう一筋縄でいかない問題を、一筋縄でいかないように取り組んで行くようにしています。

うわずみをすくうのではなく、深く掘る。

その途中で、最初考えていたものとは違う方向に行ってもかまわないんです。大事なのは深堀りしていける忍耐力と、それを怖がらず真理を探究する姿勢があれば、どこまでも応援する。それがこのゼミの姿勢です。

それは卒業後の社会生活にも大きく影響しそうですね。

自分で苦しみながら学び、そこで出た疑問を追及していく力をつければ、社会に出て、自分の前に壁が立ちはだかっても乗り越えられると確信しています。

そういった姿勢がゼミ生の学びたい気持ちを刺激している気がします。

そうですね。うちのゼミには、誰かがつくった路線にただ乗りして結果だけ享受するフリーライダーがいないのです。人数が少ない分、全員参加型ですから。みんなとても前のめりです。今、全学部で行われている討論会の学生シンポジウムも4年前にうちのゼミ生が提案して始まりました。毎年、奨学論文にも参加していて、過去2回最優秀賞を受賞しました。

すごく学ぶことに貪欲ですね。

私はもう少し「やること」を減らしてもいいと思うのですが、学生たちが許してくれません(笑)

高畠さんは姉歯ゼミに入って何が変わりましたか?

視野が広くなり、自分の中で気付けることが多くなりました。事前準備の大切さとか締め切りを守る大切さとか。まだまだですが、そういった意識を常に強く持っています。

社会人と変わらないですね。ゼミ生同士の関係はどうですか?

コミュニケーションを取る頻度が高いので学年に関係なく話しますし、仲は悪くはないですが、馴れ合いのような仲の良さではないですね。グループができて、誰かが排除されるようなことはありません。そもそも、やるべきことが多すぎて、そんな暇もないと思います。

研究する環境として理想だと思います。では、高畠さんが思う姉歯ゼミの魅力は?

一言で言えば、少数派を恐れなくていいところです。自分が周りと違う意見を持っていたとしても、ゼミ生や姉歯先生ならなぜそう思ったのかを掘り下げて聞いてもらえる。それから、先生のもとで勉強することで、新しい発見や、今まで自分になかった視点等の気付きを得られる。それがここで学ぶ醍醐味ですね。

では最後に、どういった方が姉歯ゼミに向いていると思いますか?

募集の文言の「やる気さえあれば大丈夫」がすべてです。経済学の理論もゼロからで構いませんし、レポートやレジェメの書き方やプレゼンの仕方など、社会に出たときにすぐ使えるスキルも学べます。とにかく「勉強したい」という気持ちが一番大事。それに、どうせゼミに入った途端に嫌という程文字を読み込まなければならないので、本を読む癖だけはつけておいた方がいいと思いますね。
取材時期:2018年9月

