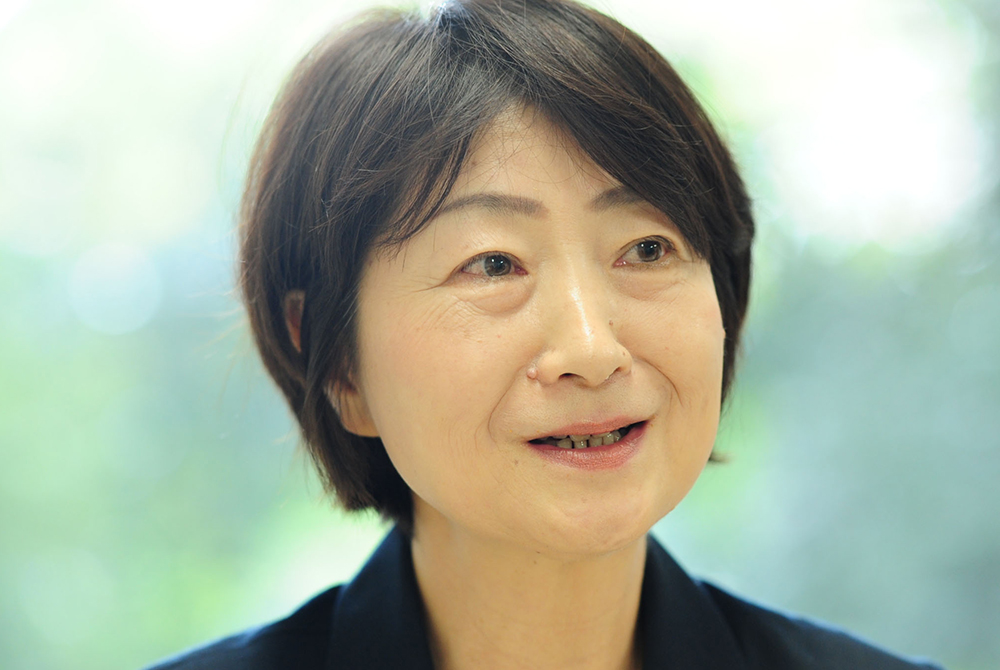
近衞 典子先生
大分県生まれ。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科中退。同大学助手、昭和学院短期大学助教授を経て現在、駒澤大学文学部教授。博士(人文科学)。専門は日本近世文学。主な著書に『上田秋成新考-くせ者の文学』(ぺりかん社刊)、『秋成研究資料集成』(監修・クレス出版刊)、『<江戸怪談文芸名作選・第四巻>動物怪談集』(校訂代表、国書刊行会)等。

諏訪 実香子さん
文学部国文学科3年生。近衞ゼミ、ゼミ生。「ゼミは、学びに主体的になれるだけではなく、意見を交わして理解が深まるのが面白いです」

泉水 友里亜さん
文学部国文学科3年生。近衞ゼミ、ゼミ生。「江戸時代の文学は日常を切り取った題材が多いので、全く知らなくても楽しいですよ」
秘密のベールに包まれた
江戸の文学の魅力


近衞先生、ゼミ生の皆さん、今日はゼミについて色々教えていただければと思います! 国文学科が充実している駒大の中で、こちらのゼミはどの時代を研究されているのですか?

宜しくお願いします。 駒大の国文学科は、全国的にみても珍しく上代(奈良時代)、中古(平安時代)、中世(鎌倉〜室町時代)、近世(江戸時代)、近現代と、すべての時代の教員が揃っているのですが、私のゼミでは江戸時代の文学を研究しています。

具体的にどういった内容なのでしょうか?

まず2年生は百人一首の読解と分析をします。ポイントは江戸時代の注釈書『百人一首改観抄』を使うこと。

それはどう違うのでしょうか?

江戸以前の中世までの学問というのは、庶民に浸透している一般的なものではなく、一部の特権階級だけが知り得るものだったんです。秘密のベールに包むことで権威を高め、選ばれた一部の人だけがその奥義を知ることができたのです。

茶道のような。

そうですね。わかりやすく言えば、老舗の鰻屋などで代々受け継がれている“秘伝のタレ”。部外者には秘匿されます。それが、江戸時代になって新しい学問の形態ができた時に、データに基づく解釈が出てきたんです。

文系なのにデータですか……!?

具体的な統計というわけではないんですが、江戸時代になって、契沖(けいちゅう)や本居宣長といった国学者が独自の方法論で研究し「この言葉はこの言葉とセットで使われている」などという用例に基づいて実証的に分析していく研究方法が確立されたんです。

例えば「梅」はどの言葉とセットになっていると思いますか?

ぱっと思いつくのは……「うぐいす」でしょうか。

それが一般的ですよね。他にも奈良の「龍田川(たつたがわ)」と言えば「紅葉」だったり、その言葉が使われている他の歌も合わせて解釈していく。

知的な連想ゲームみたいで面白いですね。

他にも、例えば「奥山に 紅葉踏みわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ 秋は悲しき」という歌。

『古今集』に出てきた有名な歌ですね。

その中に出てくる秋が、初秋か仲秋か晩秋かによって印象が変わってきますが、契沖は、この歌が『古今集』に出てくる鹿の歌五首の中の二首目であり、後の三首には萩が詠み込まれているということに注目して晩秋ではなく仲秋だと解釈したり、色々な説があるんです。

すごく奥深い! 改めて触れてみたくなりますね。

ですよね! 学んでいて、知らなかった解釈に気付いた時は、言葉の新しい扉が開くような感じがしてワクワクします。

ギアが変わる瞬間があるよね。「もっと知りたい!」って思うと、どんどん楽しくなる。

私もゼミ生と話していて「そういう考え方もあるのか」と気付きを得ることもありますよ。ですから、百人一首はあくまで素材であって、歌の意味ではなく「自分で考えて解釈する楽しさ」を体験して、培って欲しいんです。
“くずし字”の読解で
失われし文化が紡がれる
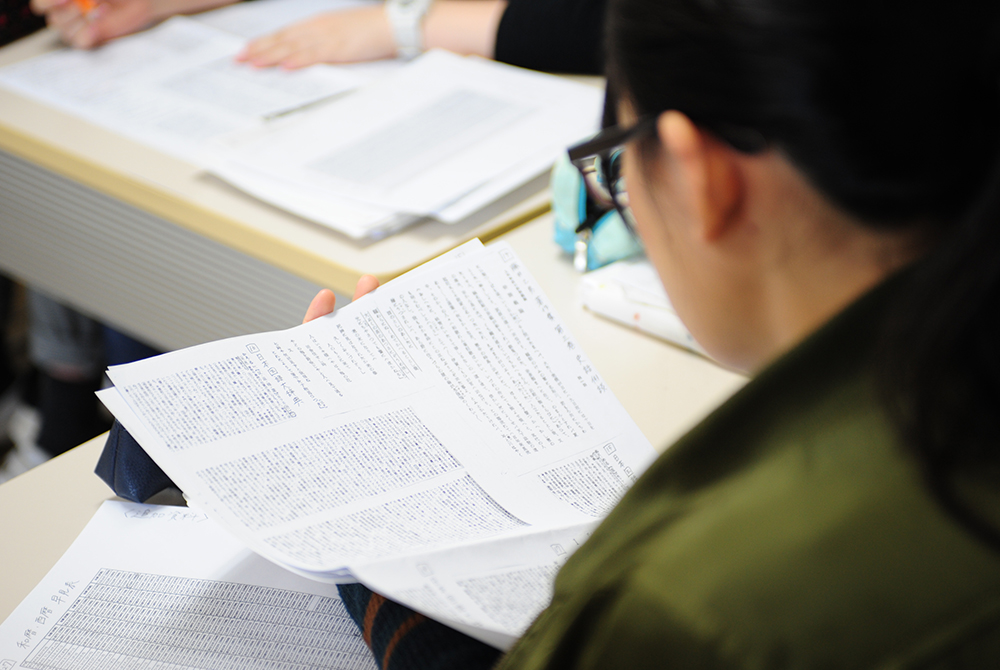

その『百人一首改観抄』は現代の言葉で書かれたものではなく「くずし字」で書かれた江戸時代の和書を使います。

どういう字なんですか?

英語の筆記体の日本語版のようなぐにゃぐにゃした文字です。

骨董品の掛け軸に書かれているような?

そう。2年生は、それをゼロからではなく、別のバージョンの活字体などを使って8割ぐらいは分かった状態で、残りを自分で考えて読解の訓練をするんです。

私は最初はどこからどこが一字かすら分からなかったです(笑)

それが読めるようになると、まだ現代の表記で出版されていない江戸時代の本が読めるようになるんです。

世界が広がりますね。

まだまだ活字化されていない江戸時代の本は沢山ありますから。くずし字が読めることで失われつつある文化を紡いでいくことができるんです。それが読める人を増やしたいという思いでゼミに取り入れています。

今、くずし字をゲーム感覚で読み解くアプリもありますよ。

アプリまで! 人知れず注目されているんですね。

現代社会に通じることもありますから。

例えばどういうことですか?

先の東日本大震災で、大津波がすぐそこまで来た場所に石碑があって、「津波がきたらここより上に逃げろ」と書いてあったのですが、くずし字で書かれていたために読めなかったそうです。

……予言ですか!?

ではなくて、歴史を調べると、かつて同じ場所で大津波があって、多くの人が犠牲になっていたんです。その地で生き延びた人たちが「後世の人に同じ悲劇を味わって欲しくない」という願いを込めて、記録として石に刻んでいた。

くずし字が読解できたことによって、先人の思いが現代に届いたんですね。ロマンティック。

そうなんです。そういったこともあって、地震研究などの理系の研究者も古文書を読解してデータをとる必要性を認識し、国文学者とも連繋するようになりました。

すごく興味深い話ですね。
新しい学問の
道を拓く喜びに満ちたゼミ


お二人はどうして近衞ゼミを専攻されたんですか?

私は、高校時代の頃から近世の文学に「人間くささ」をすごく感じていたんです。色恋とかお金の生々しい話だったりとか。今とは時代がまったく違いますが、通じる部分もあれば真逆の価値観もあって、そこに面白さを感じて。

確かに面白いよね。私は、江戸時代の文学は、高校の時の日本史の授業では名前だけが出てきて実際には読まなかったので、知的好奇心がありました。

ゼミ内はどういった雰囲気ですか?

真面目な学生が多くて、その学年にもよりますが、議論が活発ですね。

3年生は江戸時代後期の小説家、上田秋成(うえだあきなり)の俳諧を研究しているのですが、一人に三句が割り当てられて、それぞれ各自が辞典を引いたりして読み解き、自分なりの訳を発表した上で、皆でディスカッションするんです。

近衞先生が答えを示すのではなく?

私の方が少し知識がありますが、一方的に教えるのではなく、同じ地平にいて皆で考えて議論することを大事にしています。だから学生の方が良い意見を言って感心することもありますよ。

すごく有機的な関係ですね。

それがゼミの醍醐味ですから。自分で調べて新しいことを知ったり、議論して自分にない価値観に触れることで、勉強が「やらされるもの」ではなく「面白いもの」ということが実感できる場所。それが、誰も行ったことがない道を切り拓くという学問の喜びにつながるんです。

授業より深く学びが楽しめるんですね。ゼミでは座学だけなんでしょうか?

江戸を身近に感じる“文学散歩”の課外ゼミもあります。

例えばどういった場所に行くのでしょうか?

江戸時代の古民家がそのまま残っている施設に行って、昔の人の生活様式を見学したりします。

屋根が高かったり、それまで土間とか知らなかったので、楽しかったです。

生活を知ることで、より江戸時代の文学がイメージしやすくなりました。

他にも、日本橋には当時、一流の大店があったから今でも三越や髙島屋、日銀があるとか、江戸時代があった東京だからこそ今に繋がるものが発見できます。

点ではなく、今に繋がる線として見ると面白いですね。

何事にも新旧があって、必ず「旧」がないと「新」が生まれませんから。江戸時代の文学はちょうど時代の要になっていて、それ以前の古典の流れが見渡せるし、近代以降のルーツでもある。しかも、江戸時代の文学そのものも面白い。

一度その魅力を知ったら、やみつきになりますよ!
取材時期:2018年10月

